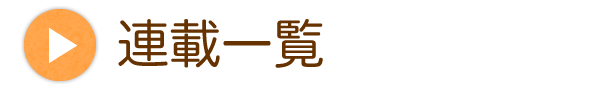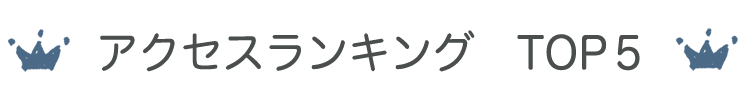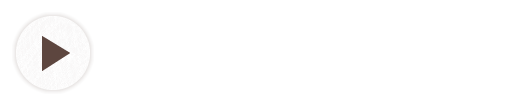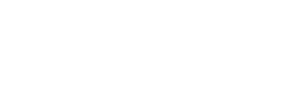�z�[�� �� �\���E���� �� �ϐk�`�F�b�N�����|�C���g�u�� �� ��2�b �ȒP�I�₳�����ϗ͕ǂ̔z�u |

�ƂÂ���̐�y�����u�C�G�}�K�T�|�[�^�[�v�ɕ����������E���s�̑̌��k����R�~���B
���̌��ނ�I���R
���R�������đI�ǍށA���A����̌��R�~�B>>
�킪�Ƃ̊O�Ǎ�
�O�Ǎނ̎�ނƋ@�\���A�F��f�U�C���ɂ��Ă��B>>
�S���R�~���X�g�͂�����
�l�C�̃f�U�C���ƁA�R�[�f�B�l�[�g�̃|�C���g�B>>
�������Ə��ނ̃J���[�R�[�f�B�l�[�g���{�ƁA�֗��ȋ@�\�����������ނ����Љ�B>>


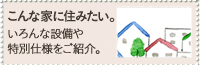
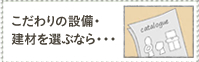
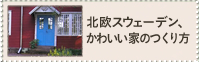
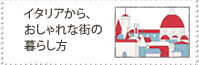
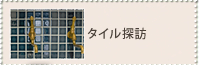



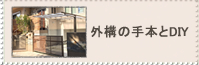



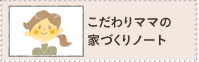
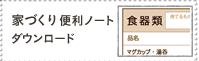
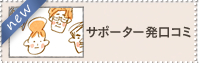

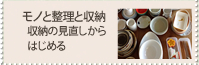

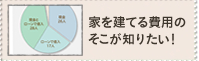
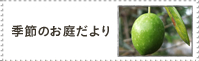
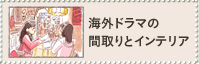
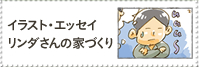
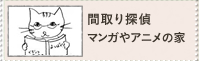
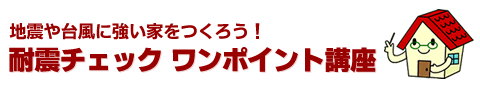 |
|||||||||
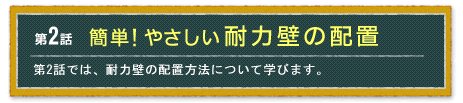 |
|||||||||
|
|||||||||
|
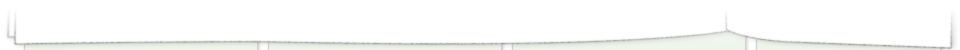 |
||||||||
|
�C�G�}�K�Ől�C�̃L�[���[�h �Ԏ��F�u�Ԏ��v�̂����� >> �E�v���ɕ����I�Ԏ��̗v�]�x�X�g3 >> ���z�����d�F���z�����d�̂���� >> |
�L�b�`���F�킪�Ƃ̃L�b�`���v���� >> ���[�F���s���Ȃ����[�v���� >> |
�����F�Ƃ����Ă��p�͂�����H >> �y�n�T���F�y�n�T����10�̃R�c >> �n�Չ��ǁF�����ƌ��R�~ >> �ƎґI�сF�Ǝ҂Ƃ̏o� >> �\���E���ށF�ϐk�����|�C���g�u�� >> �G�R�F���Ȃ��̉Ƃ͍��f�M�H >> |
�}���K�F��������D�� >> ���𗧂��F�ƂÂ���m�[�g >> �E�O�������N�F�A�[�L�f�U�C�i�[�W���p���q�p��r >> |
|||||
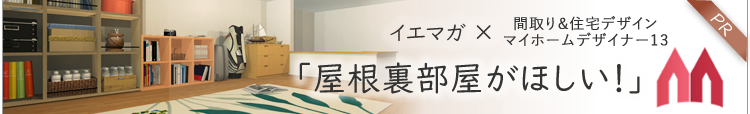
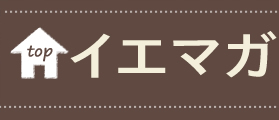
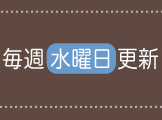




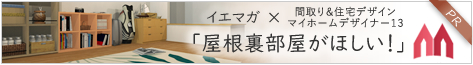












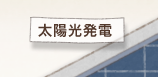
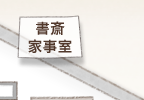


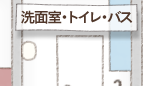

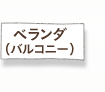
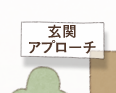
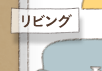


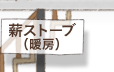

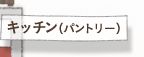



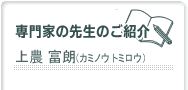
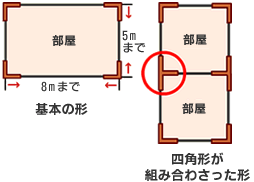 �ϗ͕ǂ́A�l�p�`����{�Ƃ��āA�R�[�i�[���ł߂Ă����̂���{�ł��B
�ϗ͕ǂ́A�l�p�`����{�Ƃ��āA�R�[�i�[���ł߂Ă����̂���{�ł��B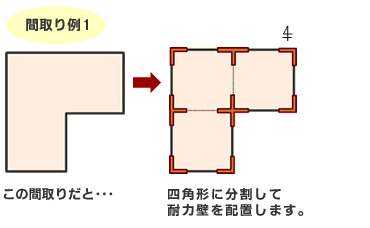
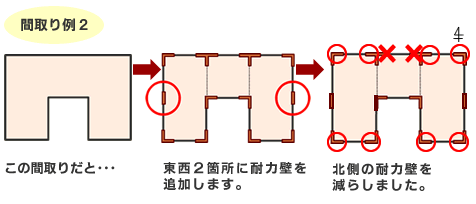
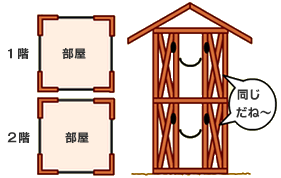 1�K��2�K�̑ϗ͕ǂ̈ʒu�́A�͂��ϓ��ɓ`���邽�߂ɁA�㉺���ł��邾�����낦��悤�ɂ��܂��B
1�K��2�K�̑ϗ͕ǂ̈ʒu�́A�͂��ϓ��ɓ`���邽�߂ɁA�㉺���ł��邾�����낦��悤�ɂ��܂��B![�����A��k���ꂼ��1/4�]�[���őϗ͕ǂ�����](img/vol02_img05.gif) ���̊Ԏ����ɍl���Ă݂܂��傤�B
���̊Ԏ����ɍl���Ă݂܂��傤�B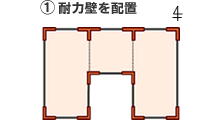 �܂��́A�l�p�`�ɕ������āA�e�R�[�i�[�ɑϗ͕ǂ�z�u���܂��B
�܂��́A�l�p�`�ɕ������āA�e�R�[�i�[�ɑϗ͕ǂ�z�u���܂��B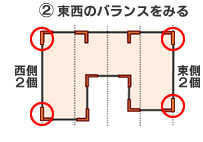 ���ɁA�����Ɠ�k�̑ϗ͕ǂ̃o�����X���l���܂��B
���ɁA�����Ɠ�k�̑ϗ͕ǂ̃o�����X���l���܂��B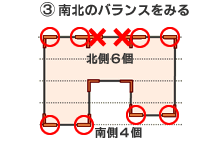 ��k�̃o�����X���l���܂��B
��k�̃o�����X���l���܂��B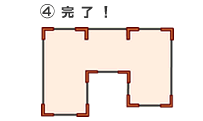 �ϗ͕ǂ́A����������Ώ�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�o�����X����邱�Ƃ���ł��B
�ϗ͕ǂ́A����������Ώ�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�o�����X����邱�Ƃ���ł��B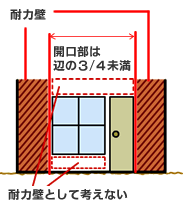 ����h�A�ɂ��ǂ̂Ȃ������i�J���j�́A���̕ӂ�3/4�����̒����ɂ���ƈ��S�ł��B �J�������͑ϗ͕ǂɂȂ蓾�Ȃ��̂ŁA�ϗ͕ǂƂ̒������K�v�ł��B
����h�A�ɂ��ǂ̂Ȃ������i�J���j�́A���̕ӂ�3/4�����̒����ɂ���ƈ��S�ł��B �J�������͑ϗ͕ǂɂȂ蓾�Ȃ��̂ŁA�ϗ͕ǂƂ̒������K�v�ł��B